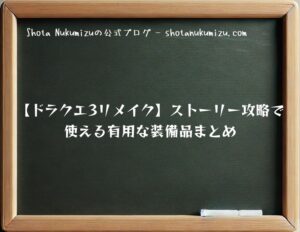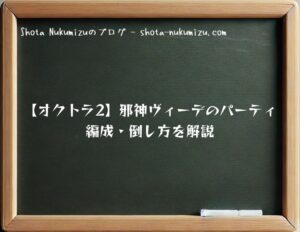【コラム】『ポケモンBW』で実存主義を解説する|自由と責任をめぐる考察
こんにちは、Shotaです。今回の記事では、普段投稿しているゲーム関係の記事とは趣向を変えたコラムを書きます。今回の記事では、ジャン=ポール・サルトルの実存主義を、任天堂のRPG『ポケットモンスター ブラック・ホワイト』(以下「BW」)を軸に解説します。
はじめに|ゲームが問いかける“生き方”の哲学
『ポケットモンスター ブラック・ホワイト』は、2010年9月18日に株式会社ポケモンから発売されたNintendo DS用のRPGです。
「ポケモンと人間の関係はどうあるべきか?」「正義とは何か?」といった問いが、物語の随所にちりばめられており、まるで哲学書のような奥行きを感じさせます。
本記事では、フランスの哲学者ジャン=ポール・サルトルの「実存主義」という考え方をヒントに、BWの物語、特に謎の青年「N」と彼が率いる「プラズマ団」の行動を読み解いていきます。
あの難解なサルトルの思想をBWのシナリオを具体例に再構築するのが本記事の主旨です。
できる限り正確な内容を心がけておりますが、多少間違っている可能性があるので参考文献も確認するようにお願いします。
サルトル哲学の基本|BWを読み解くための3つのキーワード
BWのシナリオを分析する前に、サルトルの『存在と無』で取り上げられている要点を解説します。
1. 実存は本質に先立つ
サルトルによれば、人間には「最初から決められた自分」など存在しません。
生まれたあとに、どんな行動を選び、どう生きていくかによって、自分自身を形づくっていく存在こそが人間なのです。ゲームに例えるなら、“キャラメイク”があとから始まるようなもの。私たちは常に、自分をつくり変えていける自由を持っています。
2. 「自由の刑」と「自己欺瞞」
人は自由であるがゆえに、その選択にはすべて責任を負わなければなりません。そのプレッシャーを避けるために、人はしばしば「仕方なかった」「これは自分の運命」と、自分に嘘をついてしまいます。これが“自己欺瞞”です。
サルトルは、自由であることの苦しさを「自由の刑」と呼びました。つまり、自由には逃れられない重さがあるのです。
3. 「まなざし」
私たちは他人の視線——つまり「まなざし」によって、「こうあるべき」「こう見られている」という意識を持ちます。他者からの評価は、時に自分の自由を制限し、「〇〇な人」と固定されてしまう要因になります。
人間関係とは、互いに“決めつけ”と“抗い”がせめぎ合う、自由をめぐる攻防でもあるのです。
Nの理想とプラズマ団の矛盾|善意と欺瞞のあいだで揺れる“自由”
『ポケットモンスターブラック・ホワイト』(BW)には、サルトルの実存主義がそのまま登場人物の行動に投影されているような場面が多く見られます。特に注目すべきなのが、主人公の前に立ちはだかるNと、彼が率いるプラズマ団の存在です。
彼らはそれぞれの立場から「ポケモンをどう扱うべきか?」という問いに向き合っていますが、その思想と行動には決定的な矛盾が潜んでいます。
Nが背負う「自由の刑」
Nは「ポケモンを人間から解放する」という純粋でまっすぐな理想を掲げています。彼は、ポケモンがモンスターボールという道具に閉じ込められている現状を心から嘆き、ポケモンだけの自由な世界を夢見ています。その強い想いは、電気石の洞穴での彼の言葉によく表れています。
「世界は 灰色になっていく…… ボクには それが 許せない ポケモンと 人間を 区分し 白黒 はっきり わける そうしてこそ ポケモンは 完全な 存在に なれるんだ そう! これこそが ボクの 夢! かなえるべき 夢なんだ!」
――N(電気石の洞穴 出口)
この「白黒はっきりわける」という彼の理想は、サルトル的に見ると、とても興味深いものです。人間とポケモンが共存する「灰色」の世界は、複雑で、答えが一つではありません。Nの理想は、その複雑さや曖昧さから目をそらし、「ポケモン解放こそが絶対的な善だ」と信じ込もうとする行為に見えます。
これは、自由な選択がもたらす責任の重さ、つまり「自由の刑」から逃れるための一つの「自己欺瞞」と解釈できるかもしれません。彼の純粋さは、養父であるゲーチスに与えられた考えを、疑うことなく信じ込むという危うさも持っていたのです。
プラズマ団の「大義」と「欺瞞」——理念を利用する組織
Nの純粋な理想とは対照的に、彼が率いるプラズマ団の行動は、組織的な「自己欺瞞」のお手本のようなものです。彼らは「ポケモン解放」という目的を掲げながら、実際にはトレーナーからポケモンを強奪し、ゲーチスの世界征服という野望のために利用しています。
ある団員は、自分たちの行動をこう正当化します。
「あなたたち普通のトレーナーがポケモンを使うのは悪いこと わたしたちプラズマ団がポケモンを使うのはいいこと!」
— プラズマ団員
このダブルスタンダードは、サルトルが主張している、自分たちの行動の本質から目を背ける「自己欺瞞」そのものです。しかし、物語の終盤、Nの城にいる別の団員は、この欺瞞に気づき苦悩を口にします。
「わたしたち プラズマだんは ひとから うばった ポケモンを つかっていたのよ! ポケモンって かわいそうね! つかう ひとの めいれいを むしすることなんて できないもの!」
— プラズマ団員(Nの城)
この台詞は、「ポケモンがかわいそう」と言いながら、自分たちもまたポケモンを「うばい」「つかっていた」という矛盾を自覚した、痛切な告白です。これは、サルトルが「悪意」と呼んだ、自分を偽る状態から抜け出そうとする瞬間であり、BWの物語に人間的な深みを与えています。
衝突する二つの「真実」――主人公とNの「まなざし」
『ポケモンBW』のクライマックスは、単なるバトルやストーリーの盛り上がりにとどまりません。そこには、「まなざし」を通じた主体性と信念のぶつかり合いという、実存主義の本質的なテーマが描かれています。
このセクションでは、サルトル哲学における「他者のまなざし」が、どのようにNと主人公の関係性に影響しているのかを見ていきましょう。
Nの視線が“主人公”を決めつけるとき
サルトルによれば、他人の「まなざし」は、自由な私を「こういう人間だ」と決めつけ、評価する力を持っています。Nは物語の中で、常に主人公とそのポケモンとの関係を、自分の「理想」という物差しで測り、「間違っている」と断罪しようとします。カラクサタウンでの初めての出会いで、彼はこう言い放ちます。
「キミの ポケモン 今 話していたよね…… そうかキミたちにも 聞こえないのか…… かわいそうに」
— N(カラクサタウン)
この「かわいそうに」という一言は、Nが自分の特殊能力を基準に、主人公のあり方を「間違い」だと断言する、一方的な「まなざし」です。
サルトルの言う“まなざし”とは、他人の目によって私たちの自由が制限され、「こうあるべきだ」と押し付けられる力のこと。Nはまさにその視線によって、主人公の在り方を狭めようとしているのです。
イデオロギーの対決:レシラム vs ゼクロム
物語の頂点に位置するのが、Nと主人公の最終対決。Nは「真実」を象徴する伝説のポケモン・レシラムを、主人公は「理想」を象徴するゼクロムを従え、それぞれの信念を背負って激突します。
こちらの部分は『ブラック』あるいは『ホワイト』のどちらを選んだかによって物語の方向性は変わりますが、わかりやすさを重視してこの表現にしています。
「ボクには かくごが ある! トモダチの ポケモンたちを きずつけても しんねんを つらぬく!」
— N(Nの城)
Nは「真実」を司るレシラムを、主人公は「理想」を司るゼクロムをそれぞれ従え、対峙します。伝説のポケモンは、ここではそれぞれのトレーナーが信じる「世界のあり方」の象徴となるのです。このバトルは、どちらの「真実」が世界を定義するのかを決める戦いと言えるでしょう。
主人公の勝利は、Nが信じてきた「真実」が、唯一絶対のものではなかったことを証明します。主人公がポケモンとの信頼関係を通じて示したもう一つの「真実」が、Nの「まなざし」を打ち破り、彼の世界観を根底から覆したのです。
敗北から始まる、Nの"自由な人生"
敗北したNは、ゲーチスから「化け物」と罵倒され、初めて他者から与えられた「王」という役割から解放されます。そして、自らの足で新たな「自分」を探す旅に出るのです。
これは、他者との激しいぶつかり合いを通じて、自分自身が変わっていくという、非常に人間的な成長のドラマを描いています。
プレイヤーの選択も「実存的」だった?
ここまで『ポケモンBW』の物語を通じて、Nやプラズマ団の思想や行動を哲学的に見てきました。ところが、実はこの作品が問いかけているのは登場人物だけではありません。
私たちプレイヤー自身の選択もまた、ジャン=ポール・サルトルの言う“実存的な行為”として解釈できるのです。
ゲームの中で、私たちは常に選び続けています。その選択の積み重ねが、プレイヤーごとの“トレーナーとしての人生”を形づくっていくのです。
ポケモン選びは「自分探し」の旅
ゲーム開始時、私たちは何者でもない存在としてイッシュ地方に降り立ちます。サルトルは、人間が未来に向かって自分を投げかけることを「投企」(とうき)と呼びました。
私たちは、どのポケモンを捕まえ、育て、どんなパーティを組むかという無数の選択を通じて、「チャンピオンを目指すトレーナー」「図鑑完成を目指すコレクター」「特定のポケモンを愛でるブリーダー」といった、自分だけの「トレーナー像」を自由に創造していきます。
このプロセスは、まさに「実存は本質に先立つ」というサルトルの言葉を、ゲームで体験していると言えるでしょう。
通信対戦は「他者のまなざし」との対話
通信対戦は、自分が作り上げたパーティや戦略が、他のプレイヤーという「他者」の「まなざし」に晒される真剣勝負の場です。対戦相手は、こちらの戦略を読み、こちらの自由を制限しようとしてきます。この緊張感の中で、私たちは自分の選択の正しさを証明し、勝利を目指します。
他人の視線や反応によって、自分の選択が試され、評価される――勝てば自信を得られるし、負ければ自分のやり方を見直すきっかけになります。そこには、「自由に選んだ自分」を他者に見せるという、勇気ある実存の行為があるのです。
勝ち負け以上に大切なのは、「自分がどう生きて(プレイして)いるか」に責任を持つこと。それが、実存主義の核にある「自由の本質」に通じるのです。
結論:『ポケモンBW』はプレイヤーに何を問いかけた?
ここまで見てきたように、『ポケットモンスター ブラック・ホワイト』(BW)は、ただのゲームではありません。
Nの理想と葛藤、プラズマ団の矛盾、主人公との衝突、そしてプレイヤー自身の選択——そのすべてに、「自由とは何か?」「自分はどう生きるべきか?」という問いがあります。
Nの苦悩は、“自由”と“責任”の重さだった
Nは純粋な理想を掲げながらも、その理想にしがみつくことで、曖昧な現実や多様な価値観に目を向けることができませんでした。
彼の苦しみは、サルトルが言うところの「自由の刑」そのもの。そして、その理想を支えるために自己欺瞞に陥った彼の姿は、私たち自身が“正しさ”に縛られてしまう瞬間とも重なります。
プレイヤーに向けられた根源的な問い
BWが私たちに突きつけてくるのは、極めて根源的でシンプルな問いです。
「あなたにとっての真実とは何か?」
「なぜ、あなたはポケモンと旅をするのか?」
他のシリーズ作品が「最強のトレーナーになる」といった分かりやすい目標を提示する一方、BWはその前提を問い直してきます。「ポケモンを解放すべきだ」という異論を通じて、プレイヤー自身の選択に意味と責任を問いかける作品なのです。
物語の消費者から、主体的な思索者へ
『ポケモンBW』は、こう語りかけているように思えます:
「真実はひとつじゃない。世界には多様な“真実”が存在し、それらは常に対話の中で磨かれていく。」
「そして、どんな選択をするにせよ、その責任はあなた自身が引き受けなければならない。」
この作品は、正義や自由、他者との関係といった普遍的なテーマを、“ゲーム”という形で体験させてくれる哲学的な問いの装置なのです。
BWをプレイすることは、自分の生き方を静かに見つめ直す旅でもあります。それはきっと、サルトルが言った「人は、自分で自分を創る存在である」という言葉と、どこかで重なっているのではないでしょうか。
ポケモンシリーズのシナリオは週刊少年ジャンプにおける「友情・努力・勝利」を体現したものが大半ですが、BWはシナリオの根幹に正義や自由といった、哲学的で難解な部分が含まれています。
参考文献・サイト一覧
書籍
- サルトル, J.-P. (2007). 存在と無 (松浪信三郎 訳). ちくま学芸文庫. (Sartre, J.-P. (1943). L'Être et le néant).
- サルトル, J.-P. (1996). 実存主義とは何か (伊吹武彦・海老坂武・石崎晴己 訳). 人文書院. (Sartre, J.-P. (1946). L'existentialisme est un humanisme).
- Sarah Richmond, Jean-Paul Sartre(2021). Being and Nothingless(English Edition).
WEBサイト
[1] note. (2024年4月8日). プレイしなくてもわかるポケモンの物語学:Nが嫌われる理由.
https://note.com/gomimasa_pokeboc/n/n9ad9b02ccdd2
[2] note. (2024年4月19日). プレイしなくても楽しめるポケモンの物語学:Nの成熟.
https://note.com/gomimasa_pokeboc/n/n765cd6846ef5
[3] torimoge.com. (2018年12月19日). ポケモンBW/N(エヌ)会話セリフイベント一覧.
http://torimoge.com/game/pokemon/pokemon-n/
[4] ピクシブ百科事典. (n.d.). プラズマ団.
https://dic.pixiv.net/a/%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%BA%E3%83%9E%E5%9B%A3
[5] ポケモンブラック・ホワイト攻略. (n.d.). セリフ集「Nのしろ」.
https://rainsibu.net/TPC/Poke-BW/Scenario/talk/talk_N.html
[6] Poke Sites. (2010年12月5日). ポケットモンスターBW ブラック セリフ集 6番道路~電気石の洞穴.
https://ameblo.jp/pokesites/entry-10728281689.html
おまけ
ChatGPTで生成した、ドイツ連邦軍の制服を着ている『ポケモンBW』女性主人公の画像です。